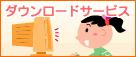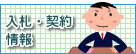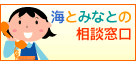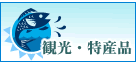歴史でみる志布志港
歴史
志布志港は古くから海を糧に栄え、平安時代末期に開かれた大隈、薩摩、日向に誇る広大な荘園・島津荘の唯一の水門(港)として、この地の発展に大きな足跡を残しています。海上交易が盛んになった江戸時代には、内外交易でひらけ、「志布志千軒の町」とうたわれるほどの町並みを形成し、活況を呈していました。
近年に至って、志布志港は鹿児島県東部地域の流通拠点港湾として整備が進められ、昭和44年4月には、国の重要港湾の指定を受けました。
現在では本港地区、外港地区、若浜地区、新若浜地区の4つの地区で形成され、中でも若浜地区は、昭和60年の埋立竣工以来、昭和62年4月の開港指定や、大型船のけい留施設等の整備による世界各国からの穀物船等の就航、臨海工業用地への大規模な穀物貯蔵施設・配合飼料製造業の関連企業等の立地により、南九州地域の物流拠点として経済発展に大きく寄与しています。
平成8年には、九州で唯一中核国際港湾に位置付けされ、外港地区にガントリークレーン、くん蒸上屋、リーファーコンセントといった施設の整備をはじめ、税関、出入国管理、検疫のCIQ機能が完備されました。
平成9年からは、外貿コンテナ貨物等による貨物取扱量の増大等に対応するため、若浜地区の南側の新若浜地区に新たな国際コンテナターミナルの整備が進められ、平成21年3月には5万トン級の大型船舶が接岸可能な岸壁が整備され、供用を開始しました。
また、平成23年5月には大型船の一括大量輸送によるバラ貨物の安価かつ安定的な輸送を実現する拠点港湾「国際バルク戦略港湾」に選定され、更なる地域産業の発展が期待されています。

中世の貿易風景

大正初期

昭和46年

昭和54年(直轄着手前)

昭和59年(若浜地区埋立慨成)

平成10年

平成18年

平成24年

令和2年
沿革
| 年次 | 出来事 | |
|---|---|---|
| 昭和 | 28年 | 地方港湾の指定 |
| 42年 | 港湾計画(外港地区の設定) | |
| 44年 | 重要港湾の指定 | |
| 47年 | 港湾計画(外港地区の拡大) | |
| 51年 | 外港地区第一突提供用開始 | |
| 52年 | さんふらわあ就航 | |
| 54年 | 港湾計画(若浜地区の埋立造成) | |
| 55年 | 外港地区第二突提供用開始 | |
| 60年 | 若浜地区竣功(107ha) | |
| 61年 | 工業用地の分譲開始(49.7ha) | |
| コンテナ定期航路開設 | ||
| 62年 | 開港指定 | |
| 植物防疫港の指定 | ||
| フェリーありあけ就航 | ||
| 63年 | 無線検疫港の指定 | |
| 出入国港の指定 | ||
| 平成 | 元年 | 検疫港の指定 |
| 5年 | 港湾計画(〜17年) 「国際コンテナターミナルの整備(新若浜地区の整備)」 「旅客船埠頭の整備(若浜地区)」 |
|
| 7年 | 蘇州号就航 | |
| 8年 | 中核国際港湾に位置付け(運輸省第9次港湾整備計画) | |
| 9年 | 動物検疫港の指定 | |
| 特定保税地域の指定(外港地区第二突堤)2.0ha | ||
| 新若浜地区国際コンテナターミナル整備着工 | ||
| ガントリークレーン1号機設置(H9.2) | ||
| 10年 | 志布志港ポートセールス推進協議会発足(H10.1.27) | |
| 11年 | 旅客船埠頭一部完成(岸壁) | |
| コンテナ定期航路開設(香港・台湾航路OOOL) | ||
| 「ふじ丸」入港(客船)商船三井 | ||
| 12年 | コンテナ定期航路開設(台湾航路 東京船舶・愛媛オーシャンライン) | |
| 14年 | 指定保税地域の追加指定(H14.2)2.0haから4.7haへ | |
| ガントリークレーン2号機設置(H14.3) | ||
| コンテナ定期航路開設(中国航路 民生輪船) | ||
| 15年 | コンテナ定期航路開設(中国・韓国航路 神原汽船) | |
| コンテナ定期航路開設(台湾航路APL) | ||
| 16年 | 旅客船埠頭完成 | |
| 指定保税地域の追加指定(H16.4)4.7haから8.4haへ | ||
| フェリーたかちほ就航 | ||
| 外貿コンテナ取扱量年間5万TEU達成(H16.11.8) | ||
| 18年 | コンテナ定期航路開設(韓国航路) | |
| 松島丸就航(沖縄航路) | ||
| 21年 | 新若浜地区国際コンテナターミナル供給開始 (H21.3.28) |
|
| 23年 | 国際バルク戦略港湾に選定(H23.5.30) | |
| 24年 | コンテナ定期航路開設(中国航路 TCLC) | |
| 29年 | 新若浜地区国際バルク戦略港湾整備着工 | |