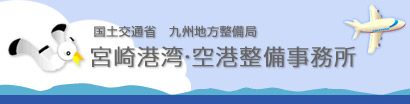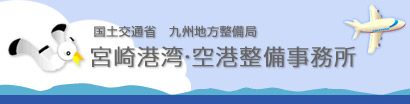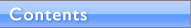
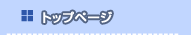
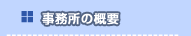
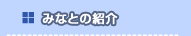
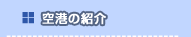
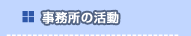
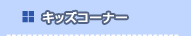
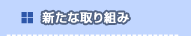
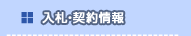
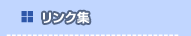

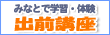
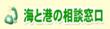
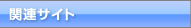

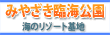

Adobe Reader
ダウンロードはこちら
|
現在の細島港は、工業港地区、白浜地区及び商業港地区からなっています。
商業港地区は、古くから天然の良港として知られていて、宋や明との中継貿易港ともなり、また南蛮貿易港としてポルトガル船の入港もありました。江戸時代には、日向諸藩や薩摩藩の参勤交代の出発港ともなって各藩の船宿が軒を連ねるなど、東九州の海上交通の要衝でした。
明治のはじめは、沖縄、鹿児島方面より京阪神方面に向かう通商船舶が入港する程度でしたが、明治13年に四国阪神方面との定期航路が開設され、本港の利用は次第に増加してきました。
明治20年オランダ人デレーケ技師の設計によって近代的な港湾改修工事が進められ、明治27年に県費支弁港に、大正元年には指定港湾に編入されました。
また、大正12年に日豊線、細島港線の鉄道開通に伴い貨物の集散が急増し、昭和2年には第2種重要港湾に編入され、さらに昭和7年から昭和15年にかけて内務省直轄による港湾整備が行われました。 |
|
戦後、県総合開発計画の一環として、昭和22年度より港湾整備計画に基づき、桟橋、浚渫ならびに陸上施設などの改修工事を進め、昭和26年1月には重要港湾に指定されました。その後、昭和27年より臨海工業地帯の造成と工業港の建設に着手されました。
以来、工業港地区において工業用地の造成をはじめ港湾施設の整備増強が進められ、昭和38年までに公共岸壁6バース、大型荷役機械、タグボート、公共貯鉱場、県営上屋、臨港道路などが整備されました。昭和39年11月開港以来、国内船はもちろん、各国の大型船舶が相次いで入港し、名実ともに大型港湾としてその機能を発揮しています。さらに、昭和44年度、45年度で公共岸壁3バースが増設されています。
白浜地区においては、昭和45年度に石油配分基地の造成、46年度に木材基地の造成が行われ一層港湾機能は増大し、昭和46年5月15日には本県でただ一つの港則法にもとづく特定港の指定を受けました。
平成5年に韓国・釜山港との間に外貿コンテナ定期航路が開設されて以来、神戸航路、台湾航路が次々に開設されています。これらの航路開設に伴い、コンテナ取扱量も順調に伸び続けてきています。
また、平成12年には国際化に伴う貨物船の大型化等に対応するため、国及び県が整備を進めてきた多目的国際ターミナルが完成し、対岸には効率的な輸送となるようコンテナ貨物とバルク貨物を分離したバルク専用の国際物流ターミナルが平成27年6月に完成しており、益々国際貨物輸送の中核として期待されています。
本港の背後圏においては、東九州自動車道等の陸上交通網の整備が完了しており、本港の東九州における交通の結節点としての重要性が今後飛躍的に見込まれます。
細島港はこのような背後圏の要請に対応した物流機能の充実を図るとともに、港内静穏度の向上を図るための外郭施設等を整備し、新たな21世紀の国際港を目指しています。 |
|
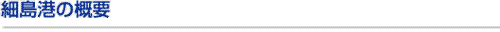
| ■所在地・・・・・・・・・・・・・・・・・日向市 |
| ■港湾区域告示・・・・・・・・・・・昭和28年3月 |
| ■港湾区域面積・・・・・・・・・・・1,289ha |
| ■重要港湾指定・・・・・・・・・・・昭和26年1月 |
| ■入港船舶数(R2)・・・・・・・3,217隻 |
| ■入港船舶総トン数(R2)・・5,712千トン |
■取扱貨物量(R2)・・・・・・・3,564千トン |
|
※令和2年度は速報値
|
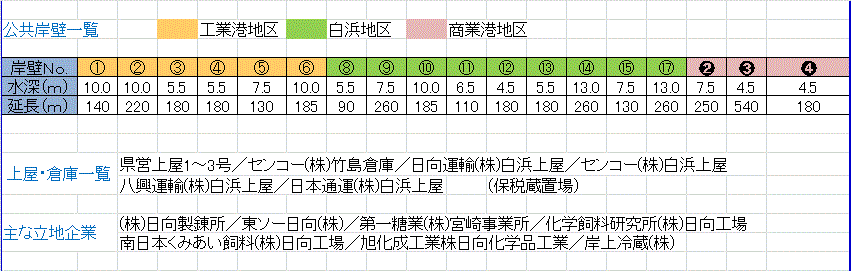
|
|