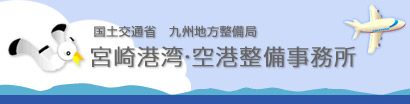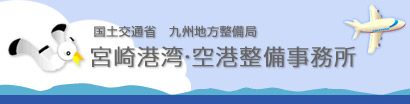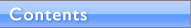
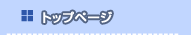
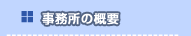
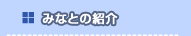
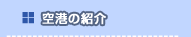
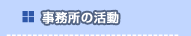
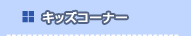
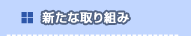
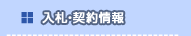
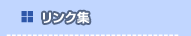

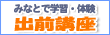
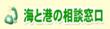
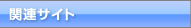

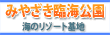

Adobe Reader
ダウンロードはこちら
|
宮崎港は、古くは赤江港と呼ばれていました。大淀川の河口港として鎌倉時代より船舶の往来が盛んで、江戸時代には阪神方面との交易が開け、林産物・農産物を移出し、加工品などを移入していました。
一方大淀川は、台風時の洪水、大規模な河口の移動、閉塞などで、たびたび舟運が妨げられていました。明治20年代にようやく河口の切開工事が行われ、明治33年には日向汽船が設立され、神戸・大阪・鹿児島・多度津との間に350総トン級の汽船が就航するまでになりました。しかし、航路の維持が困難で、大正期に入ると宮崎鉄道や国鉄日豊線が開通したことによる輸送体系の変革で、港勢は衰退し、以後長く低迷することになりました。 |
戦後、宮崎市の発展につれ、再び港湾整備が強く望まれるようになり、昭和32年から港湾改修事業による河口の導流堤建設、それに続く一連の物揚場、岸壁の建設等により、取り扱い貨物が大幅に伸びてきました。
しかし、大淀川河口港では、船舶の急速な大型化に対応できないため、大型港湾としての整備が強く求められてきました。
このため昭和48年3月、新たに砂州を切り開いてこれを港口とし、15,000トン級の貨物船等を受け入れる大型港湾を建設する港湾計画が策定され、同年4月重要港湾に指定されました。また、直轄宮崎港工事事務所が設置されました。 |
宮崎港は、古くは「赤江港」と呼ばれており、大淀川を河口港とした小さな港でした。その後、背後圏の経済発展の必要性から港湾整備が要請され係留施設や外郭施設の整備が順次進められてきました。
これらの港湾整備に伴い、平成2年に大阪港とを結ぶフェリーが就航して以来、カーフェリーやROROの船の航路が次々に開設され、現在は関西圏を結ぶ定期船が就航しており、内貿貨物を中心に港湾取扱貨物量は県一を誇っています。
|
| 本港は空港や高速道路と直結する等南九州の交通の要衝にあることから、南九州の物流拠点として内貿ユニットロードの増加に対応できる岸壁の整備など流通機能の充実を図るとともに、港内の静穏と船舶航行の安全性の向上を図るための外郭施設などを整備し、観光宮崎の海の玄関口としてふさわしい港湾づくりを目指しています。 |
|
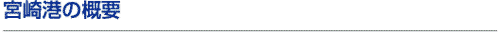
| ■所在地・・・・・・・・・・・・・・・・宮崎市 |
| ■港湾区域告示・・・・・・・・・・昭和38年6月 |
| ■港湾区域面積・・・・・・・・・・・1,983ha |
| ■重要港湾指定・・・・・・・・・・昭和48年4月 |
| ■入港船舶数(R2)・・・・・・・3,265隻 |
| ■入港船舶総トン数(R2)・・5,893千トン |
| ■取扱貨物量(R2)・・・・・・・6,521千トン |
※令和2年度は速報値
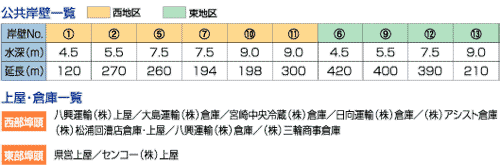
宮崎港岸壁位置東
宮崎港岸壁位置西
|
|